まだ先の話ですが会社を退職しサイドFIREした後の健康保険について考えたいと思います。
サイドFIRE後に直面する「健康保険問題」
会社員であれば、会社で健康保険に加入し、会社が保険料の半分を負担してくれていました。しかし、退職すると一旦その会社の健康保険は解約することになります。
退職後、無保険状態は絶対にNGです。
なぜなら、日本は「国民皆保険」制度を導入している国です。国民は基本的に必ずいずれかの公的な医療保険制度に加入することを義務付けられています。
仮に保険に未加入で、入院や手術になれば、医療保険がなければ数十万円〜数百万円の出費もありえます。
50代はまだ医療リスクが低いとはいえ、生活習慣病や突然の病気の可能性もゼロではありません。そのため、セミリタイア後の生活を安心させるために、医療保険の仕組みと選択肢を理解する必要があるかと思います。
退職後に選べる医療保険の4つの選択肢
退職後の医療保険の選択肢は大きく4つです。
- 任意継続被保険者制度を活用する
- 国民健康保険に入る
- 配偶者の扶養に入る
- 健康保険に入る
1. 任意継続被保険者制度を活用する
退職前に加入していた健康保険(第2号被保険者)を最長2年間継続できる制度です。
- 条件:退職前に継続して健康保険を2カ月以上加入していること
- 保険料:全額自己負担(会社負担分も含むので今までの2倍)
- メリット:手続きが簡単、医療機関の変更なし
- デメリット:2年経過後は自動的に終了
保険料は標準報酬月額で計算されますが、上限があるため、高収入だった人には有利なケースもあります。
2年目の保険料は、前年の所得に基づいて計算されません。1年目の同額の保険料を支払う必要がありますので注意が必要です。
2. 国民健康保険に入る
会社員がサイドFIRE後、多くの方が加入するのが国民健康保険(第1号被保険者)です。
- 管轄:市区町村
- 保険料:前年の所得に基づいて計算されます
- 注意点:退職直後は前年の収入が高いため、初年度は保険料が高額になりがち
ただし、翌年度以降は収入が減る場合は、保険料も下がります。
3. 配偶者の扶養に入る
もし配偶者が会社員や公務員であれば、扶養に入って第3号被保険者になることも選択肢です。
- 条件:年収130万円未満(見込み)
- メリット:保険料負担ゼロ
- デメリット:働き方に制約が出る(収入を扶養内に抑える必要あり)
サイドFIRE後もパートや副業をする場合、年収130万円を超えると扶養から外れるため、収入調整が必要です。
扶養に入ると失業給付は受給できませんのでご注意が必要です。
4. 健康保険に入る
フルタイムの会社を退職した後、別の会社でパートやアルバイトとして働き、退職前と同じように2号被保険者として健康保険に入ることも選択肢です。
- 条件:週の勤務が 20時間以上、基本給与が月額 88,000円以上、2ヶ月を超えて働く予定がある、学生ではない
- メリット:会社が保険料の半分を負担、将来貰える厚生年金の受給額がアップ。
- デメリット:週3~4日は働く必要がある。
こちらは会社は変わりますが、健康保険は継続するケースです。現時点で私はこの選択肢は考えていませんが、今後法律が変わり、週の勤務時間や月額の上限が下がった場合は、十分検討する価値はあると思っています。
任意継続被保険者制度と国民健康保険どちらを選ぶべき?
不要に入るケースを除くと、退職後の1年目は、任意継続か国民健康保険のどちらに入ることになります。
一般的に、年収400万円以下なら国民健康保険、500万円以上なら任意継続が支払う金額が有利といわれています。
※保険料は市区町村で異なるため、必ず窓口で確認してください。
国民保険の「減免制度」について
国民健康保険料には、「減免制度」がり、自治体に申請を行うことで保険料の減免や軽減措置を受けられる場合があります。
- 低所得者(収入がある一定の額を下回っている)
- 非自発的失業による減収(倒産、解雇など)
- やむを得ない理由(リストラ、通勤困難、家族の事情、病気など)で大幅な収入減
自治体によって基準や手続きやルールは異なるため、必ず市区町村ごとの窓口で確認してください。
私は自発的失業になると思いますので、減免制度は無理ですね。
健康保険のまとめ
会社を退職しサイドFIREした後の医療保険の計画は必須です。ポイントは次のとおりです。
- 健康保険の選択肢を把握する
- 任意継続、国民健康保険、扶養を比較、検討
- 保険料試算をしてキャッシュフローを確認
- 所得調整や減免制度を活用
サイドFIREは「お金を増やす」だけでなく、「お金の流れを管理する」ことが重要です。健康保険の対策はその第一歩です。
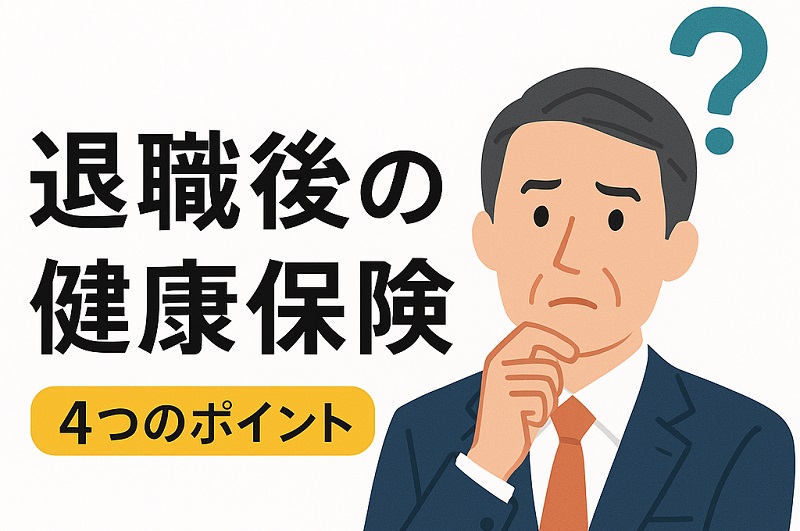

コメント